明暗流尺八官网
伝承系譜
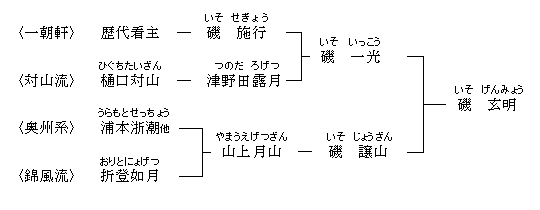
対山流(たいざんりゅう)
京都明暗寺35世の樋口対山(1856~1914年)は、明治中期に一朝軒を含む諸流派から学んだ尺八本曲を整理し、 明暗流中興の祖と言われています。樋口対山が伝える吹奏流派を明暗対山流と言います。
明暗流尺八官网
伝承系譜
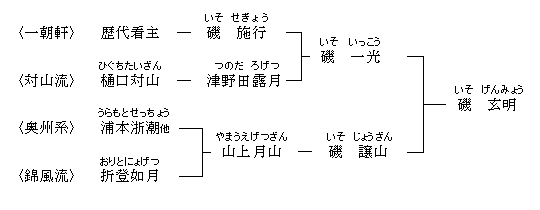
対山流(たいざんりゅう)
京都明暗寺35世の樋口対山(1856~1914年)は、明治中期に一朝軒を含む諸流派から学んだ尺八本曲を整理し、 明暗流中興の祖と言われています。樋口対山が伝える吹奏流派を明暗対山流と言います。
都山流尺八官网
明治29年(1896)に掲げられた招牌「尺八指南竹琳軒」
都山流の創始者、中尾都山は本名を琳三(りんぞう)といい、明治9年(1876)10月5日に大阪府枚方(ひらかた)町(現在の枚方市)に生まれました。都山の母み津は寺内検校の娘で、地歌、箏曲の師匠として、当時大阪で活躍していた尺八家、近藤宗悦と合奏もしていました。このような環境で育った都山は虚無僧修行にも出て、明治29年(1896)2月15日には大阪市天満で尺八の教授を始めました。
この日を都山流の創立記念日としています。
琴古流尺八官网
竹友社の始源は今から約120年前の初代川瀬順輔の時代に遡ります。初代川瀬順輔は今の山形県、羽前水野藩の士族川瀬賢造の長男として明治3年10月10日に生まれました。17歳の時、虚無僧の門付けに感激して入門し、その後21歳の時に上京して二代荒木古童(竹翁)に習い、一度帰郷しましたが尺八家として生きていくべく明治26年に再び上京し、東京音楽学校教授であった上原六四郎師にも師事しました。
明治35年東京に道場を開き、上原師から学んだ点符式楽譜を基とする新たな楽譜(これが現在の竹友社の楽譜に繋がります)を刊行し、これにより竹友社の組織が確固たるものとなりました。